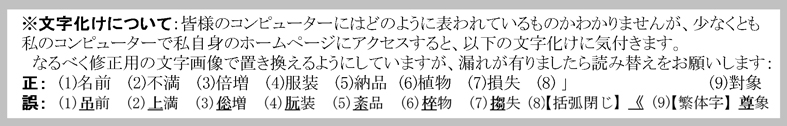
1)トップ・ページに戻る 2)目次のページに戻る 3)『読書メモ』のページに戻る
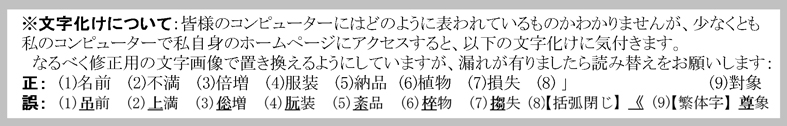
2009年10月30日初版第1刷発行 論創社
まえがき
エッセイを読んだ友人が、半世紀近い私と中国の関わりを~一冊の本にまとめたら、と~ その勧めに甘えて、私の中国観の変遷を、中国の五〇年の歴史をふりかえりつつ書き進めた。
かつての私は新生中国に見せられ、良くも悪くもリアルな目で中国を見ることができなかった。「人民民主主義共和国![]() という中国のおこなうことは多少の誤謬があっても、発展途上にあるのだと信じる、まさに「折り紙つきの中国派
という中国のおこなうことは多少の誤謬があっても、発展途上にあるのだと信じる、まさに「折り紙つきの中国派![]() であった。その私が、今やすっかり醒めた目で中国を見るようになっている。~
であった。その私が、今やすっかり醒めた目で中国を見るようになっている。~
今後ますます肥大化していく中国は、日本にとって「厄介な隣国![]() だという感は否めない ~
だという感は否めない ~
二度目の訪中から帰った七二年、田中角栄首相が北京に行き、~ 日本と中華人民共和国は国交を樹立、それまで国交のあった台湾(中華民国)には断交を通告した。「樹立![]() としたのは、今の私には「国交回復
としたのは、今の私には「国交回復![]() や「国交正常化
や「国交正常化![]() 等の言い方に抵抗があるからだ。人民共和国成立後の二三年間は、ずっと国交がなかったのだから「回復
等の言い方に抵抗があるからだ。人民共和国成立後の二三年間は、ずっと国交がなかったのだから「回復![]() ではないし、責任をすべて日本にかぶせるようにも受け取れる「正常化
ではないし、責任をすべて日本にかぶせるようにも受け取れる「正常化![]() もおかしいと思う。~
もおかしいと思う。~
こうした中国側の御都合主義に対するモヤモヤは、この頃からだんだん私の胸中に醸(かも)し出されて行った。私の中国認識の転換の始まりであり、徐々に中国を相対化して見るようになっていった。
当時、中国はソ連社会帝国主義を孤立させるためにはアメリカ、日本とも手を組もう、と明らかに路線を変更した。ニクソンと田中角栄の訪中はその線上にあった、と見ていいだろう。
一体中国は、「ソ連社会帝国主義![]() についてどう見ていたのか。一九七六年一月一七日の「~に対する人民日報論評
についてどう見ていたのか。一九七六年一月一七日の「~に対する人民日報論評![]() ~を見てみよう。
~を見てみよう。
覇権外交のみにくい演技
ソ連のグロムイコ外相は最近、一九六六年以来第三回目の訪日を行った。五日間にわたるはりつめた活動と激しい論争がかわされた会談の中で、この超大国の外相は日本にさまざまな威かく・買収の手口を使い、さまざまなみにくい演技を披露し、ソ連の覇権主義の正体を一層あきらかにさらけだした。(中略)ソ連外相は日本において、口を開けば「ソ連は一貫して日本との善隣関係の強化を主張している![]() などといい、同時にこれはソ連の「根本国策
などといい、同時にこれはソ連の「根本国策![]() であるともいっている。
であるともいっている。
いっていることは耳ざわりが良いが、やっていることは卑劣である。日本人民はこれについては切実な体験者である。次のことを見ていただきたい。長期にわたって日本固有の領土、歯舞、色丹、国後、択捉の四島を強引に力づくで占領し、これを拒み続けて返還しないのは、他でもないソ連である。大量の漁船をくり出して、常に日本の近海、はては領海まで侵入し、漁業資源を略奪し、日本人民に甚大な搊害を蒙らせ、ひどい場合には日本の領海で日本漁船をたえず強奪し、日本漁民を連行しているのは、これも他ならぬソ連である。人にはいわれない目的で、軍艦や軍用機を日本周辺の海上に度々送り込み、空中であばれまわり、公然と日本の領海、領空を侵犯しているのも、やはり他ならぬ、ソ連である。ソ連社会帝国主義の所行に、何処にいささかなりとも「善隣![]() の誠意があるのか、あるのはこれとは反対の掛値なしの超大国の覇権主義的「国策
の誠意があるのか、あるのはこれとは反対の掛値なしの超大国の覇権主義的「国策![]() である。(後略)
である。(後略)
北方四島の部分を尖閣諸島に入れかえれば、このソ連のふるまいは、失礼ながらそのまま現在の中国に当てはまるのではないだろうか。
この本を書くにあたって一九七一年九月~七二年二月の『朝日新聞』縮刷版で検証してみた。
林彪は、実は七一年九月一三日早朝、~で墜落死している。~ 七二年二月になっても、トップ記事に「林彪 失脚後も健在![]() とある。フランスの国会議員団が訪中、中国高官に林彪のことを質問したら、「政治的ミスと個々の人間の問題とを、我々は決して混同しない、林彪は失脚後も健在
とある。フランスの国会議員団が訪中、中国高官に林彪のことを質問したら、「政治的ミスと個々の人間の問題とを、我々は決して混同しない、林彪は失脚後も健在![]() と答えたそうな。フランスもコケにされたものだ。
と答えたそうな。フランスもコケにされたものだ。
七一年八月から、『朝日新聞』で本多勝一記者の「中国の旅![]() の連載が始まった。彼は「私の訪中目的は……戦争中の中国における日本軍の行動を、中国側の視点から明らかにすることだった
の連載が始まった。彼は「私の訪中目的は……戦争中の中国における日本軍の行動を、中国側の視点から明らかにすることだった![]() (『中国の旅』朝日新聞社)と「日本軍国主義の罪業
(『中国の旅』朝日新聞社)と「日本軍国主義の罪業![]() を中国べったりの立場で糾弾、日本社会に大きな影響を与えた。
を中国べったりの立場で糾弾、日本社会に大きな影響を与えた。
話は少々それるがこの時期『朝日新聞』は「チュチェ(主体)の国、北朝鮮![]() という連載もしている。七二年一二月二日付の第一六回「清津の涙
という連載もしている。七二年一二月二日付の第一六回「清津の涙![]() には、第一六一次帰国船として万景峰(マンギョンボン)号が清津港につき、みな喜びの涙にくれた、としている。出迎えの当局者は、帰国者が北朝鮮に足を踏み入れたとたんから、生活の一切を保障する、と言い切っている。さらに、ずっと前の帰国船で帰ったある朝鮮人に、日本では汚い長屋住まいだったが、今はオンドルつきの三DKで幸せに暮らしている、と語らせている。
には、第一六一次帰国船として万景峰(マンギョンボン)号が清津港につき、みな喜びの涙にくれた、としている。出迎えの当局者は、帰国者が北朝鮮に足を踏み入れたとたんから、生活の一切を保障する、と言い切っている。さらに、ずっと前の帰国船で帰ったある朝鮮人に、日本では汚い長屋住まいだったが、今はオンドルつきの三DKで幸せに暮らしている、と語らせている。
このように、中国、北朝鮮を無条件に良い国と見なす風潮が、『朝日新聞』だけでなく、当時のメディアのほとんどを蔽っていた。
しかし、例外はあった。一九六六年から『サンケイ新聞』北京支局長として文革を取材していた柴田穂氏は、~ 街の至るところに貼られている壁新聞を丹念に読んでいったという。
年が明け、一月も半ば過ぎのある日、北京市党委員会の前に人だかりがしている。写真をベタベタ並べたポスターを見てアッと驚いたという。批判大会の“現場写真”で「百醜図![]() と書いてある。
と書いてある。
何と彭真元北京市長を始め、羅瑞卿(解放軍総参謀長)、田漢(劇作家、中国の国歌「義勇軍行進曲![]() の作詞者)といった大物が、首に大きな吊札をぶら下げ、両手をねじ上げられている。柴田氏は持っていたカメラでこれを写し、郵便局にかけつけて日本に送った。この写真は日本社会に大きなショックを与えた。
の作詞者)といった大物が、首に大きな吊札をぶら下げ、両手をねじ上げられている。柴田氏は持っていたカメラでこれを写し、郵便局にかけつけて日本に送った。この写真は日本社会に大きなショックを与えた。
今は『産経新聞』(サンケイは漢字に変った)の読者である私だが、当時は「サンケイなんて右翼の新聞でしょ?![]() と見向きもしなかった。でも当時この写真は、どこかで見た覚えがある。~
柴田氏ほか他の社の記者も、真実を伝えようとする人は北京にいられなくなり、一九七〇年にはついに『朝日新聞』の秋岡家栄北京支局長たった一人になってしまった。~
と見向きもしなかった。でも当時この写真は、どこかで見た覚えがある。~
柴田氏ほか他の社の記者も、真実を伝えようとする人は北京にいられなくなり、一九七〇年にはついに『朝日新聞』の秋岡家栄北京支局長たった一人になってしまった。~
氏の『北京特派員』(朝日新聞社)に、「一人ぼっちの日本人記者![]() という章がある。
という章がある。
周(注:恩来)首相からねぎらいの言葉がかかった。もちろん、それまでにも私が周首相の目にとまっていたことは確かだが、直接声をかけられたのはこれが最初である。北京に赴任してから満三年目のことであった。NHK記者の再入国拒否、共同通信支局閉鎖のあとをうけて、北京における日本人特派員は私一人になっていた。
おそらく天に昇るほど嬉しかったのだろう。中国の要人との人脈を自慢げにひけらかす「日中友好人士![]() を、イヤというほど見て来た私には、氏の得意さがよく分かるのだ。中国側にしてみれば「当時の日本国内は、プロレタリア文化大革命を正しく理解しようとする勢力に較べ、それを非難する動きの方がかえって目につくような情勢であった
を、イヤというほど見て来た私には、氏の得意さがよく分かるのだ。中国側にしてみれば「当時の日本国内は、プロレタリア文化大革命を正しく理解しようとする勢力に較べ、それを非難する動きの方がかえって目につくような情勢であった![]() と説く秋岡氏は、まことに「愛(う)い奴
と説く秋岡氏は、まことに「愛(う)い奴![]() であり、使い勝手もよかったろう。
であり、使い勝手もよかったろう。
秋岡氏は中国側の気にさわることは一切報道せず、先述のように林彪の一件などは中国の新聞同様ずっとシラを切り通した。帰国後、おそらく退職後だろうが『人民日報』海外版の日本総代理店をまかされたとは、まことに語るに落ちる話である。
あとがき
傘寿を迎えた私が、~ 中国との関わりを懸命に検証しようと試みたことは、自分にとって気にかかっていたことの精算が少しはできたのではないかとホッとしていたその矢先、衆議院選挙で自民党が惨敗し~政権が交代するという事態を迎えた。
民主党の真の実力者である小沢一郎氏が、一〇〇人もの日本人を引き連れて訪中した折、胡錦濤に対し、あたかも冊封国家の使者が皇帝に朝貢をするときのように、揉み手をせんばかりに挨拶した姿が、私にはどうしても気にかかる。~
かつて社会主義中国に魅せられた日本人の多くは、新生中国のやることに批判的ではなかった。だがいまや中国は世界第二位の経済大国になり、世界中から資源も技術も、領土さえをも取り込む勢いだ。その上敵対する国家もないのに、軍備も年々増強している。
そんな中国の実態をきちんと把握していかなければ、日本の将来への上安は増大するばかりだ。子も孫もない私だが、わが国の前途が心配でたまらない。私の心配が杞憂で終ることを願っている。
~
1)トップ・ページに戻る 2)目次のページに戻る 3)『読書メモ』のページに戻る