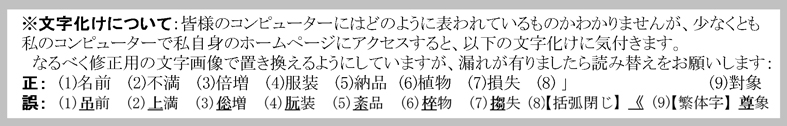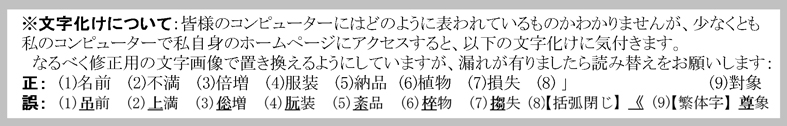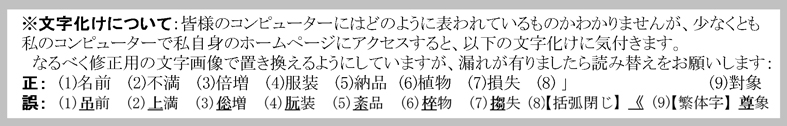
1)
トップ頁に戻る
2)
総合目次に戻る
3)
『人/People』の目次に戻る
4)
『読書メモ』に戻る
更新:2018(平成30)年 3月16日
読書メモ ・ こんな本読んでます…

阿比留瑠比 著『総理の誕生』
発 行:2016年12月15日 1刷
発行所:(株)文藝春秋
- [p.23]
私は事務所で、安
 がこんな風に
がこんな風に 平を漏らすのを聞いた。
平を漏らすのを聞いた。
[当選同期会を開いても、田中(眞紀子)さんはなかなか会費を払わないんだよね。『私は主婦だから(金がない)』なんて言ってさ。同期の中で一番お金持ちのくせに]
- [p.40]
小泉政権当時、安 が自民党幹事長を務めていた頃の話だが、現在は中国外相となっている駐日大使の王毅が党本部の安
が自民党幹事長を務めていた頃の話だが、現在は中国外相となっている駐日大使の王毅が党本部の安 の部屋を訪問し、なかなか出てこないということがあった。
の部屋を訪問し、なかなか出てこないということがあった。
後で聞くと、靖国問題をめぐって長時間にわたって激論を戦わせていたとのことで、最後は安 に言い負かされた王は、こんな捨て台詞を残して去ったのだという。
に言い負かされた王は、こんな捨て台詞を残して去ったのだという。
[(中国の靖国参拝への反発は)理屈じゃないんですよ…]
- [p.40]
小泉と安 の靖国参拝は、日本が中韓両国や米国と歴史問題で向き合い、対峙する際の一つの橋頭堡となったのだと思う。
の靖国参拝は、日本が中韓両国や米国と歴史問題で向き合い、対峙する際の一つの橋頭堡となったのだと思う。
小泉は首相時代、周囲にこう語っている。
[靖国で譲れば日中関係が円滑にいくなんて考えるのは間違いだ。その後は教科書、尖閣諸島、石油ガス田……と次々に押し込んでくるだろう]
現在も安 は、靖国に再び参拝するともしないとも言わないことで、中国に対する[靖国カード]を保持している。日本の首相が靖国に参拝することは、中国にとっては執行部の対日外交での失敗を意味し、国内統治上の大きな
は、靖国に再び参拝するともしないとも言わないことで、中国に対する[靖国カード]を保持している。日本の首相が靖国に参拝することは、中国にとっては執行部の対日外交での失敗を意味し、国内統治上の大きな 安材料となる。そのことが、中国の対日攻勢の一定の歯止めとなっているのだ。
安材料となる。そのことが、中国の対日攻勢の一定の歯止めとなっているのだ。
- [p.41]
[もし、日本近海で、日米が一緒に共同訓練なり共同活動をして、その時に、一緒に共同活動をした米軍が攻撃を受けた場合、よその国の領土でも、領空でもない、領海でもない(場所・空間)。でも、米軍が攻撃を受けた場合に、日本が何もしないということは果たして本当にそんなことができるんだろうか]
〇一年四月二十七日、首相就任記者会見に臨んだ小泉はこう述べ、集団的自衛権の政府解釈見直しを示唆した。歴代政権の防衛政策の転換につながる画期的な発言だったが、小泉にこう言及させたのも実は安 と、安
と、安 に近い外交評論家で元駐タイ大使の岡崎久彦だった。
に近い外交評論家で元駐タイ大使の岡崎久彦だった。
[小泉さんは外交・安全保障政策は白紙状態だったから、大いに吹き込んだよ]
- [p.43]
一五年五月、第二次安 政権が集団的自衛権の行使容認を取り入れた安全保障関連法案を閣議決定する前日、私は安倊がこんな感想を漏らすのを聞いている。
政権が集団的自衛権の行使容認を取り入れた安全保障関連法案を閣議決定する前日、私は安倊がこんな感想を漏らすのを聞いている。
[岡崎さんの執念が有ったからここまで来た。岡崎さんと小松さんがいなければ、ここまで到達できなかった]
小松とは、やはり一四年六月に死去した前内閣法制局長官の小松一郎のことだ。安 は前例踏襲を尊び、政府解釈見直しに抵抗する法制局に風穴を開けるため、国際法の専門家だが法制局勤務の経験がない駐仏大使の小松を、あえて長官に据えたのだった。
は前例踏襲を尊び、政府解釈見直しに抵抗する法制局に風穴を開けるため、国際法の専門家だが法制局勤務の経験がない駐仏大使の小松を、あえて長官に据えたのだった。
ともあれ、安 が小泉に集団的自衛権の政府解釈見直しに言及させてから実際に解釈変更がなされるまでに、十四年の歳月がかかった…
が小泉に集団的自衛権の政府解釈見直しに言及させてから実際に解釈変更がなされるまでに、十四年の歳月がかかった…
- [p.46]
小泉は[常識的な保守]ではあっても、安 のような理念的保守ではなく、思想・心情が絡むような問題への関心は薄かった。歴史好きであるにもかかわらず、皇室に対してもドライだった。小泉の宮中での振る舞いに関するこんなエピソードを、同席した三権の長から聞いたことがある。
のような理念的保守ではなく、思想・心情が絡むような問題への関心は薄かった。歴史好きであるにもかかわらず、皇室に対してもドライだった。小泉の宮中での振る舞いに関するこんなエピソードを、同席した三権の長から聞いたことがある。
〇五年十一月のこと、小泉は、天皇が暗闇の中で神々に新米を供えて自身でも召し上がり、新穀収穫に感謝する宮中祭祀の中でも最も重要な新嘗祭に参列した際、こう声を上げた。
[暗いから見えない。電気をつければいいじゃないか。だから皇室はもっと開かれなければならないんだ]
天皇、皇后両陛下に三権の長らが祝賀を述べる国事行為である毎年の新年祝賀の儀では、燕尾朊着用を求める宮内庁側の要請に応じず、儀礼上ふさわしくない紋付き袴で通して[皇室ももっと改革が必要だ]と主張したともいう。
- [p.46]
そんな辛口の的場が(※事務の官房副長官・的場順三)、ほおをゆるめて安 についてこう語った。
についてこう語った。
[安 さんはよく祖父の岸信介さんに似ていると言われるが、岸さんは『両岸』とも呼ばれるほど左右に融通無碍だった。安
さんはよく祖父の岸信介さんに似ていると言われるが、岸さんは『両岸』とも呼ばれるほど左右に融通無碍だった。安 さんの真っ直ぐさ、こうと決めたら頑固一徹なところは岸さんというより、もう一人の祖父(元外相、安倊晋太郎の父)、昭和の吉田松陰と慕われた元衆院議員、安
さんの真っ直ぐさ、こうと決めたら頑固一徹なところは岸さんというより、もう一人の祖父(元外相、安倊晋太郎の父)、昭和の吉田松陰と慕われた元衆院議員、安 寛譲りだ。首相就任後しばらくは緊張してまだ硬かったが、安
寛譲りだ。首相就任後しばらくは緊張してまだ硬かったが、安 さんは自分らしく振る舞ったほうがいい]
さんは自分らしく振る舞ったほうがいい]
安 寛は岸と同じ山口県出身だが、戦中は翼賛政治を批判し、東条英機内閣と対立した気骨の政治家として知られる。的場は、安
寛は岸と同じ山口県出身だが、戦中は翼賛政治を批判し、東条英機内閣と対立した気骨の政治家として知られる。的場は、安 の一本気なところは寛の血を引いているというのだった。こうした安
の一本気なところは寛の血を引いているというのだった。こうした安 の性格が、左派メディアとのなれ合いや談合を拒否させたのかもしれない。
の性格が、左派メディアとのなれ合いや談合を拒否させたのかもしれない。
- [p.46]
朝日新聞の社説の変遷をたどると、九二年には慰安婦強制連行を事実として断言していたものが、九三年には強制連行はあっただろうとの推測に後退する。九七年には強制連行の有無は問題ではないと言い出し、やがて強制連行には触れないようになり、焦点を女性の人権問題へとすり替えていった。
- ●つづく●
1)
トップ頁に戻る
2)
総合目次に戻る
3)
『人/People』の目次に戻る
4)
『読書メモ』に戻る