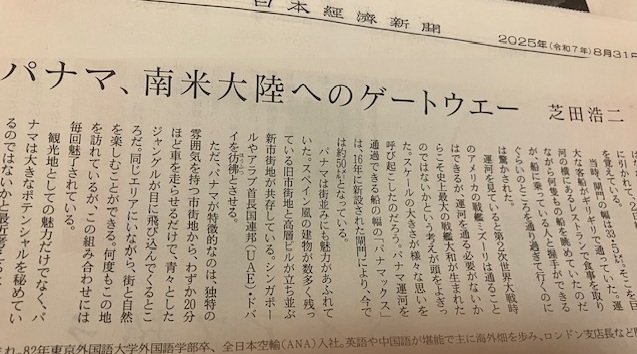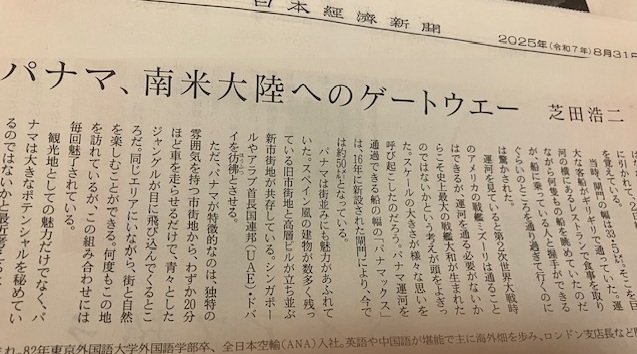2010年、中米のパナマを初めて訪れた。航空連合「スターアライアンス」の業務の一環だったが、以前から是非行ってみたいと思っていた場所だった。

何といっても圧倒されたのがパナマ運河の存在だった。太平洋とカリブ海(大西洋)とを結ぶ運河の長さは約80㌔㍍。「水のエレベーター」を使って、湾との標高差が30㍍近くある人造湖・ガトゥン湖まで船を引き上げて対岸まで渡る。そして、再びエレベーターを下っていく。水位の差を調整する閘門を開閉するのは近隣のジャングルに降った雨の水を利用していると聞いた。日本ではなかなか味わうことができない風景に引かれて、2日続けて見に行ったのを覚えている。

当時、閘門の幅は33・5㍍。そこを巨大な客船がギリギリで通っていた。運河の横にあるレストランで食事をとりながら何隻もの船を眺めていたのだが、船に乗っている人と握手ができるぐらいのところを通り過ぎて行くのには驚かされた。

運河を見ていると第2次世界大戦時のアメリカの戦艦ミズーリは通ることはできるが、運河を通る必要がないからこそ史上最大の戦艦大和が生まれたのではないかという考えが頭をよぎった。スケールの大きさが様々な思いを呼び起こしたのだろう。パナマ運河を通過できる船の幅の「パナマックス」は、16年に新設された閘門により、今では約50㍍となっている。

パナマは街並みにも魅力があふれていた。スペイン風の建物が数多く残っている旧市街地と高層ビルが立ち並ぶ新市街地が共存している。シンガポールやアラブ首長国連邦(UAE)・ドバイを彷彿とさせる。

ただ、パナマが特徴的なのは、独特の雰囲気を持つ市街地から、わずか20分ほど車を走らせるだけで、青々としたジャングルが目に飛び込んでくるところだ。同じエリアにいながら、街と自然を楽しむことができる。何度もこの地を訪れているが、この組み合わせには毎回魅了されている。

観光地としての魅力だけでなく、パナマは大きなポテンシャルを秘めているのではないかと最近考えるようになってきた。交通の結節点としてだ。日本から見ると南米は地球の反対側で、たどり着くまでに非常に時間を要する。例えば以前、ブラジルの首都・ブラジリアに行った際には、アメリカで乗り換え、パナマを経由したことで、到着するまでに35時間を要した。

もし、既に中南米のハブ機能をもつパナマに日本から直行便が飛ぶことができ、スムーズかつ快適に乗り継ぐことができれば、南米までの時間距離は一気に縮まることになる。ブラジリアまでも25時間は切るだろう。

将来、パナマが日本から南米大陸へのゲートウエーになる日を心待ちにしている。
芝田浩二 ANAホ-ルディングス社長。1957年鹿児島県生まれ。82年東京外国語大学外国語学部卒、全日本空輸(ANA)入社。英語や中国語が堪能で主に海外畑を歩み、ロンドン支店長など歴任。2022年から現職。保有するパスポートは12冊目。