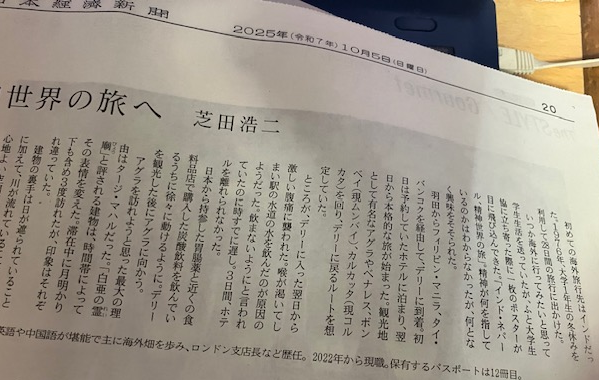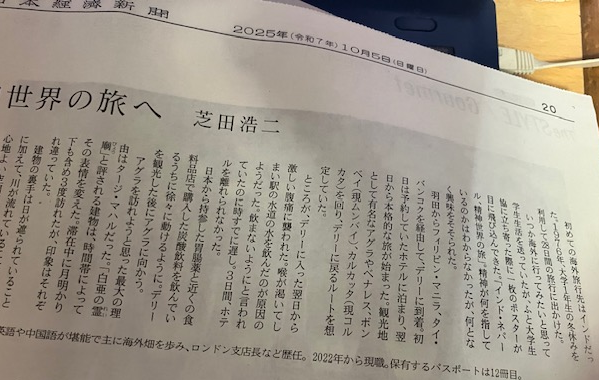初めての海外旅行先はインドだった。1976年、大学1年生の冬休みを利用して28日間の旅行に出かけた。

いつか海外に行ってみたいと思って学生生活を送っていたが、ふと大学生協に立ち寄った際に一枚のポスターが目に飛び込んできた。「インド・ネパール、精神世界の旅」。精神が何を指しているのかはわからなかったが、何となく興味をそそられた。

羽田からフィリピン・マニラ、タイ・バンコクを経由して、デリーに到着。初日は予約していたホテルに泊まり、翌日から本格的な旅が始まった。観光地として有名なアグラやベナレス、ボンベイ(現ムンバイ)、カルカッタ(現コルカタ)を回り、デリーに戻るルートを想定していた。

ところが、デリーに入った翌日から激しい腹痛に襲われた。喉が渇いてしまい駅の水道の水を飲んだのが原因のようだった。飲まないようにと言われていたのに時すでに遅し。3日間、ホテルを離れられなかった。

日本から持参した胃腸薬と近くの食料品店で購入した炭酸飲料を飲んでいるうちに徐々に動けるように。デリーを観光した後にアグラに向かう。

アグラを訪れようと思った最大の理由はタージ・マハルだった。「白亜の霊廟」と評される建物は、時間帯によってその表情を変えた。滞在中に月明かり下も含め3度訪れたが、印象はそれぞれ違っていた。

建物の裏手は日が遮られていることに加えて、川が流れていることもあり、心地よい空間が広がっていた。大理石の床に寝転んで昼寝をしていたが、気付いたら施しを受けていたのだ。それも3人から。

次のベナレスでは初日にガンジス川で沐浴をした後、またおなかを壊したが、デリーでの出来事で耐性がついたのか、大ごとにはならなかった。

ただ、その後は沐浴をせずに河原に座って周りの様子を見ていた。河原には十数㍍ごとに焼き場があり、ひっきりなしに亡くなった方を火葬していた。火の勢いが落ちると燃料としてザラメを投入し、燃え切ると灰を川に流し、そして素焼きのつぼにガンジス川の水をくんできて、焼き場をきれいにする。そこに人がいた痕跡は完全に消えていた。「生」と「死」の垣根の低さに思いいたった。

前半の腹痛による停滞が響き、カルカッタには向かわずボンベイの滞在を経て、デリーの初日に泊まったホテルに戻った。生協で申し込んだ約20人がこのホテルに集合して帰国する予定だったが、2人戻ってこなかった。

海外旅行はその後数多く経験したが、この時ほど苦しいことはなかった。出発時には62㌔㌘あった体重は帰国時には53㌔㌘まで減っていた。

どんな状態になっても「死んでたまるか」という精神を宿すきっかけとなった旅だった。
芝田浩二 ANAホ-ルディングス社長。1957年鹿児島県生まれ。82年東京外国語大学外国語学部卒、全日本空輸(ANA)入社。英語や中国語が堪能で主に海外畑を歩み、ロンドン支店長など歴任。2022年から現職。保有するパスポートは12冊目。